
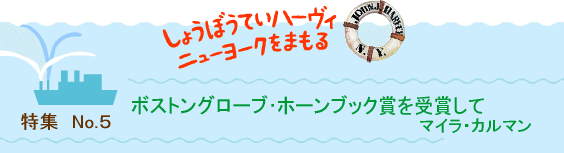
|
私は、私です。できることなら私もアニメの『ポパイ』のように、「俺は俺だ」でおしまいにしたいところですが、今日はそういうわけにはいかないようです。本当は何ごとも簡潔が一番と思っていますし、よほどいい話題がたくさんあるとか、場を盛り上げる必要があるのでもない限り、話は短い方がよいといつも考えているのですが。
――私は、私です。なぜかと聞かれたら、私はこう答えます。
汗っかきの祖母が、ウクライナの原生林のそばを流れるスルチ川で服を洗ったから。その森には野生のイチゴが生えていて、母が、きょうだいたちと一緒にイチゴを摘んだから。母は、ぼさぼさで青みがかった灰色の髪をしており、その姉と2人の兄は落ち着かない目をした子どもで、きょうだい4人とも、頭が切れて、先が読めて、とがった鉤鼻と鋭いまなざしをして、口調は辛らつだったから。
祖父が1931年に、家族を残して、誰も名前を思い出せない船で国を出て、1933年に移民受け入れ枠の割り当てをもらって家族を呼び寄せたから。ナチスが故郷の村を壊滅させた時にも、家族が生き残ることができたから。いたるところピンク色と黄色の、砂だらけでひたすら暑い、当時はまだ正式な国家ではなかった新天地へと向かう、1000人かそれよりわずかに少ない客を乗せたポラニア号という船の上で、母がオレンジをひとつ食べたから。
白いオーガンジーの服が似合う、なかなかおしゃれだった母が、はためく日よけの下で麻やピケ織りの木綿を着た人たちがタンゴを聴きながら腰を下ろしているカフェで、無頓着にオーガンジーを着たから。また私のたったひとりの姉は背が高くやせっぽちで、両手を腰に当ててひじを張ったポーズがひょろひょろだけれど美しく決まっていて、キモノを着るのが好きだったから。
父が、残念なことにちょっと変わり者で、それも残念なことにいい意味での変わり者ではなく、住んでいたテルアヴィヴのアパートの2階の窓枠から落ちたのに、何かに当たって跳ね返り、全くの無傷ですんだから。それに仕事の都合だとあれこれ理由をつけて、私たち家族を遠い国の新しい家へと移らせたから。
そのときの旅は飛行機で24時間もかかり、機内の男の人たちは灰色のスーツを着てスコッチを飲み、そうするうちにドシンとぶつかるような音がして、そうして到着したのが、ハンバーガーとオニオンが鉄板で焼かれる最高においしそうな匂いが街中に漂っている、灰色で陰鬱で勤勉な街ニューヨークだったから。
私がすっかりお祝い気分でコカコーラを飲んだから。
それからとりわけ印象的なことに、暮らしていたホテル・モンテレーの一室に大きなテレビが運び込まれ、私たちは床に座っていつまででもと見続け、そんなに見ないほうがいいとか見てはいけないとか、誰も言い出すことがなかったから。
とても上品で華奢な家具の上のほうで、空気中のほこりが太陽の光の中に漂っていたから。そして、窓のそばに近づきすぎると外へ吸い出されて死んでしまうと信じていたから。
――こういう理由で、私は私なのです。
*
私たちは街を離れました。次に待っていたのは牧歌的な郊外の暮らしで、ピアノとダンスのレッスンに通ったり、窓からヘンリー・ハドソン・パークウェイを眺めて、赤い車が何台、青い車が何台、緑の車が何台、黄色い車が何台、と数えたりして過ごしました。よく覚えていないのですが、たぶん黒い車も数えたと思います。夜は長く、人々の身なりはきちんとしていました。
また、私はペン習字をとても一生懸命練習しました。青か栗色のパーカーのボールペンが大のお気に入りで、どんな単語でも正しく綴ろうとがんばりました。
それから、インドの男の人が我が家を訪ねてきたこともあります。とてもあか抜けていて、とてもエレガントな人でした。また、住んでいたアパートは明るく、窓に近づくことは以前ほど怖くなくなりました。
父はドイツ製品を買うことをたいへん厳しく禁止していましたが、それが撤回されて、ドイツのグルンディッヒ社製のステレオを買いました。父が子守歌代わりに私に歌って聞かせてくれたのは『ネヴァー・アゲイン』で、そういう生い立ちはわたしにとって少なからぬ意味があります。
他にもいろいろな出来事がありました。テルアヴィヴに住むおばから毎週手紙が届き、おばが書いてよこす日々の暮らしは、我が家とは別の暮らしなのですが、でもとてもよく似ていました。
また、よそ者、それも完全なよそ者であることは、悲しくも恥ずかしくもありませんでした。ただ素直にものごとを見られず、同時に自信過剰でもありました。
母が私を図書館に連れて行き、ひたすらアルファベット順に本を読んでいったこともあったようです。私のバレエの先生は髪を太い三つ編みにしていて、黒いスーツを着たやせた男の人が先生の音楽教師で、たぶん恋人でもあるようでした。友だちのジュディは赤毛で鼻の形がよく、私の鼻とは似ていないけれどきれいな鼻でした。
たしか、活きたロブスターをウインドウに置いているイタリアン・レストランの近くだったと思いますが、ジョンソン通りにファッション・バーンという洋服店があり、そこでマドラス木綿の洋服を一揃い買ったこともありました。
最近そのことを思い出したら、ふとこんな想像が浮かびました。
もしジェイン・オースティンが同じ中学校に通っていたとしたら、きっと一番の仲良しになって、
「マイラ、あなたのそのマドラスの服、すごく素敵ね。ファッション・バーンで買ったの?」
なんて言われていたかもしれません。それからジェインは、私にはさっぱり意味の分からない、先分かれの多い枝みたいな文章を図解するのを手伝ってくれて、せかしたりしないで、おばかさんね、と言って笑顔まで見せてくれたかもしれません。ビロードのような内面をした傷つきやすい心を抱える、のんきなおばかさんの私に。
その後私は、不思議で夢を見ているような毎日を過ごすうちに今の仕事をするようになるのですが、その間の日々のことは言葉ではとても説明できません。ただ強いて言えば、何かが起こっていて、それが別の何かへとつながっていくかもしれないという、漠然とした感覚を持っていたことは確かです。
本を書けるかもしれない。何かを創り出すことができるかもしれない。そんな、雲をつかむような感覚でした。とらえどころのない夢でした。
そして現在。
文章を書いたり絵を描いたりするようになった私は、喜劇が性に合っていることに気づきました。ばかばかしい話も、実は完全に意味が通っているものです。ばかげた話と悲劇が紙一重なのは、皆さんもよくご存知ですよね。
人生はエピソードの積み重ねです。ちょっとした脱線が次々起こって、退屈なんてしている暇はありません。私はいつも、たわいのない失敗とか、思わぬ発見とか、日々起こるくだらない事件に大喜びしてしまいます。ちょっと変わった出来事と、誰かだけに特別な出来事。そういうものに。
人を物笑いの種にするつもりは全くありません。むしろ、人間とはなんと大胆で勇敢なのだろうだと思っているからこそです。それに、何かにとことん夢中になれる人が、私は大好きなのです。
ところで私は楽天的なタイプですが、実は「何か恐ろしいことが今すぐにも起ころうとしている」といつも考えている心配性な一族の出身です。
そう、何か恐ろしいことは必ず起こります。
そして、それは起こりました。元に戻ることのない大異変が。
消防艇ハーヴィのことを書いてみないかというお話があったとき、得意分野ではないからと1度はお断りしました。しかしハーヴィの共同所有者の方々のお話を聞かせていただき、こんなふうにすれば表現できるのではないか、という方法を思いつくことができました。
物語は1931年のニューヨークから始まります。私にとってニューヨークは過去も現在も、そしてこの先もずっと、地球という惑星のエネルギーの中枢です。私はこの街の地下鉄の話を書いたことがありましたが、そのときのやり方はもう使えませんでした。この消防艇の話では、大切なのは本筋から離れないことでした。
ふざけないこと。軽薄になったり、表面的になったりしないこと。感傷的にならないこと。単なる愛国的な話にしないこと。子どもにもおとなにも、これこれをすべきだという押し付けをしないこと。そして、ただ淡々とストーリーを語り、この世界では恐ろしい出来事が確かに起こりうるのだということを伝えることが大切でした。
そこからまた人々は前へ進んでいきます。いったいどうやって進んでいくのでしょう? そもそも、なぜ前へ進もうとするのかさえ私にはわかりません。けれども人は前へ進みます。立派な人物になんてならなくてもいいのです。ペン習字がじょうずになる必要もありません。
できることはひとつだけです。どんな自分であっても自分らしく生きること、精一杯生きることなのです。
あの恐ろしい出来事のあと、私の胸には重苦しさが居座っていて、この先も消えそうにありません。けれどもこの街、この街の人々、この街の活気が、私には誇らしくてたまりません。どうにかなるさと思えてきます。わけもなく安心できるのです。不思議でわくわくするような、愉快な気持ちになってきます。
この街には、消防艇ジョン・J・ハーヴィに乗って9月11日の燃えさかる火と戦った人々がいます。皆さんが聞きたいと思うのは、そういう人々の話に違いありません。彼らは実際的で、ロマンチックで、控えめで、勇敢です。経験したことを惜しみなく私に話してくれたことに、心から感謝しています。
9月11日の出来事は、これからの私たちに計り知れないほど大きな影響を及ぼしていくに違いありませんが、今はまだそのほんの一部が見えてきたにすぎません。私たちが最終的にどうなるのか、誰にもわからないのです。もし窓から吸い出されずに生きていられたら、私は将来も文章を書き、絵を描いていたいと考えています。私が毎日を旅する中で出会う、誰かだけに特別な、ちょっと変わった出来事、取るに足らない出来事、そして素敵な人々と素晴らしい人生を題材にして。
<翻訳・静間知子>
(05/09/20)
|
|

|


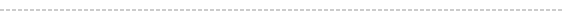




|

|
作者:マイラ・カルマン ニューヨーク在住の画家、イラストレーター。絵本作品も多数あり、最近では“What Pete Ate from A−Z”や“Smartypants(Pete in School)”などがある。また、人気ブランド《ケイト・スペード》とのコラボレーションも評判を呼んでいる。
|

訳者:矢野顕子 シンガー・ソングライター&ピアニスト。1955年東京生まれ。幼少時からピアノを始め、高校在学中よりジャズクラブ等で演奏、 76年、アルバム「JAPANESE GIRL」でソロデビュー。81年、シングル「春咲小紅」が大ヒット。以後も、普遍的な「愛」をテーマに、ジャンルにとらわれない音楽活動を続け、高い評価を得ている。90年、一家でニューヨーク州へ移住。2001年9月11日には、自宅の窓から炎と黒煙を吐くツインタワービルを目撃した。2004年10月、「ホントのきもち」をリリース。
|

|

|

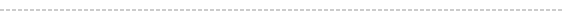

|